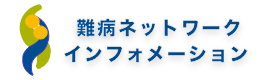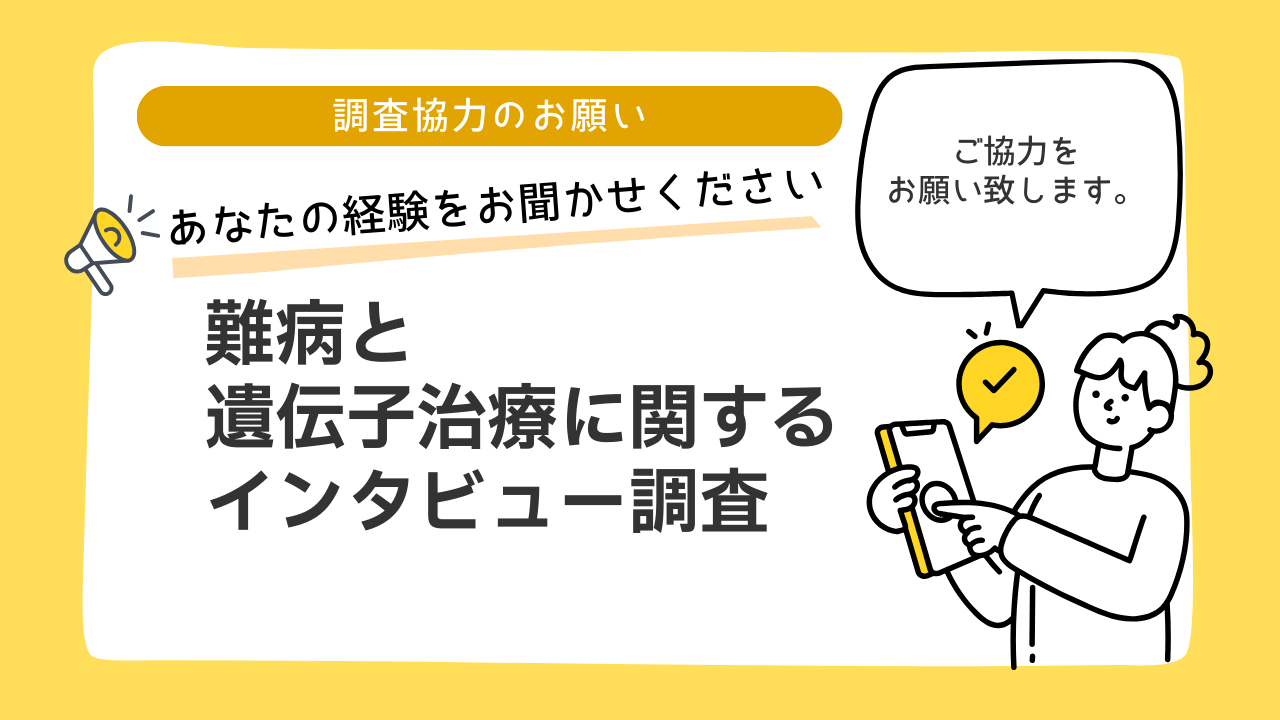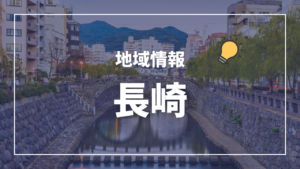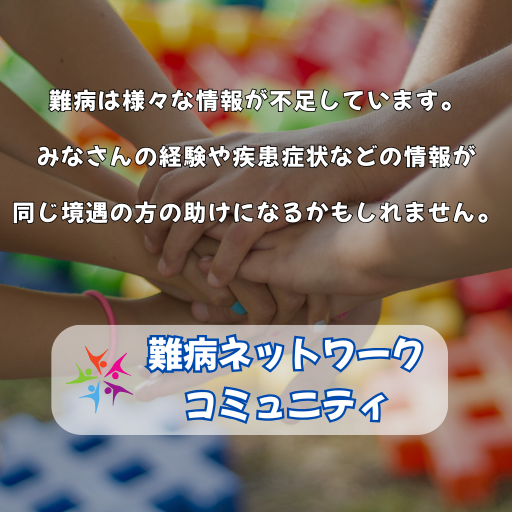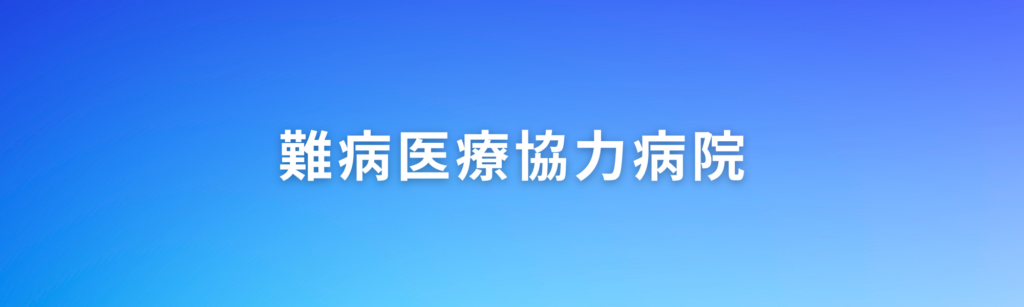京都大学大学院医学研究科の研究チームは2025年8月2日、難病「視神経脊髄炎(NMO)」において病気の発症・進行に関わる特定のB細胞サブセット「CD21 lo B細胞」を特定したと発表しました。この発見は、これまで不明だった中枢神経系での免疫反応メカニズムを解明し、新たな治療標的の可能性を示す画期的な研究成果です。
視神経脊髄炎(NMO)とは
視神経脊髄炎は、視神経や脊髄を中心に炎症が起こる自己免疫疾患で、再発を繰り返すことで視力障害や歩行障害などが生じる難病です。多くの患者の血液中でアクアポリン4を標的とする自己抗体が確認され、この自己抗体が神経を傷つけることが知られています。しかし、その抗体を作る元となるB細胞が中枢神経でどのように変化するかは分かっていませんでした。
革新的な研究手法による病態解明
髄液と血液の詳細解析
研究チームは、病気の急性期にある患者さんの髄液と血液を調べ、高性能なフローサイトメーターを用いて免疫細胞を詳しく分析しました。髄液は中枢神経(脳と脊髄)を満たしている透明な液体で、脳内の炎症状態を直接評価できる重要な検体です。
CD21 lo B細胞の特定と機能解明
分析の結果、急性期の患者さんでは、特定のB細胞の集団(CD21 lo B細胞)が髄液中で増加しており、これらが抗体を作る細胞に変化している可能性があることを発見しました。CD21 lo B細胞は、B細胞の中でもCD21という分子の発現が低い細胞群で、活性化状態にあり、自己免疫疾患で増加することが知られています。
新たな治療標的としての可能性
病気の再発との関連性
この研究で特に重要な発見は、CD21 lo B細胞の変化が病気の再発のしやすさとも関係していたことです。これは、このB細胞サブセットが単に病気の結果として現れるのではなく、実際に病気の進行に積極的に関与している可能性を示唆しています。
新たな治療戦略への展望
これらの発見により、NMOの新たな治療標的としてCD21 lo B細胞に着目する有用性が示されました。従来の治療法とは異なるアプローチで、より効果的な治療法の開発が期待されます。
研究の社会的意義と今後の展望
希少疾患研究の困難を乗り越えて
研究を主導した錦織隆成特定助教(研究当時は博士課程学生)は「急性に発症する希少疾患を対象としたため、限られたデータと向き合う困難もありましたが、得られた知見が新たな治療の手がかりとなり、患者さんの未来に繋がることを願っています」とコメントしています。
国際的な評価
本研究成果は、英国の権威ある国際学術誌「Brain」8月号に掲載され、国際的にも高く評価されています。視神経脊髄炎という難病の"しくみ"に迫る基礎研究として、世界の研究者から注目を集めています。
まとめ
この研究は、視神経脊髄炎の病態メカニズムの解明において重要な進歩を示しています。特に、末梢血だけでなく髄液においても、自己抗体をつくる免疫細胞のサブセットが大きく変化していることが明らかになったことで、今後の治療法開発に新たな道筋が示されました。
CD21 lo B細胞を標的とした治療法の開発により、視神経脊髄炎患者の再発抑制や症状改善につながる可能性があり、この基礎研究の成果が一日も早く実際の治療に応用されることが期待されます。