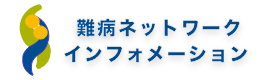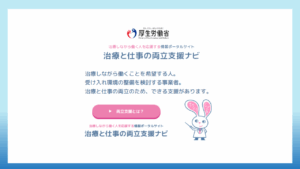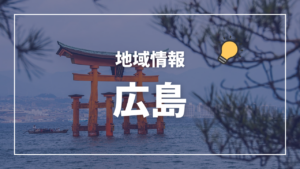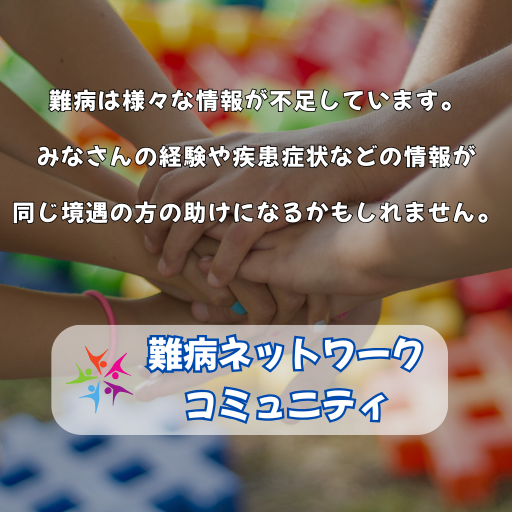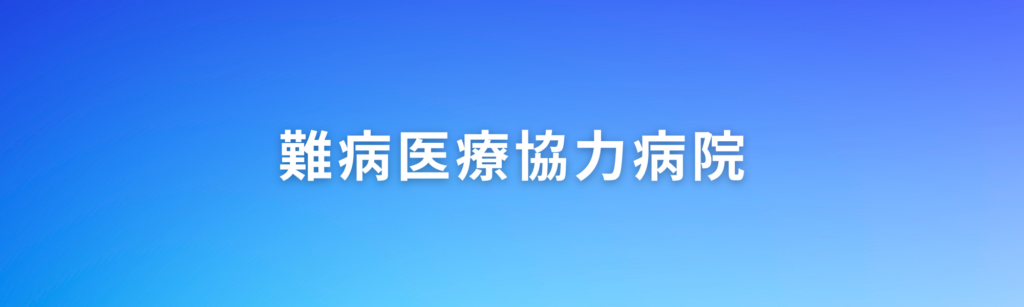治療法の劇的な進歩により予後が大幅改善
2025年7月18日、国立循環器病研究センター(国循)は、指定難病である「慢性血栓塞栓性肺高血圧症(CTEPH)」について、最近10年間で死亡リスクが87%減少したという画期的な研究結果を発表しました。この研究により、治療法の進歩が患者さんの生命予後を劇的に改善させていることが明らかになりました。
慢性血栓塞栓性肺高血圧症(CTEPH)とは
慢性血栓塞栓性肺高血圧症は、肺動脈に血栓が残って血流が慢性的に悪くなり、肺高血圧を引き起こす病気です1。進行すると右心不全を起こし、生命に関わる深刻な疾患です。現在、全国で約4,000~5,000人の患者さんがいると推定されており、厚生労働省の「指定難病」に認定されています。
以前は有効な治療法が限られており、多くの患者さんが適切な治療を受けられない状況でした。しかし、近年の医療技術の進歩により、治療選択肢が大幅に拡大しています。
革命的な治療法の発展
3つの画期的治療法の導入
研究では、治療法の発展に応じて1980年から2023年までを3つの時期に分類して分析しました
初期(1980-1999年)
- 有効な治療法がほとんどない時代
- 65%の患者が適切な治療を受けられない状況
中期(2000-2010年)
- 2000年に肺動脈血栓内膜摘除術(PEA)が本格導入
- 治療を受けられない患者が36%まで減少
後期(2010-2023年)
- 2010年にバルーン肺動脈形成術(BPA)が登場
- 肺高血圧症治療薬の開発も進展
- 治療を受けられない患者はわずか3%まで減少
マルチモーダル治療の確立
最も重要な進歩は、**PEA、BPA、薬物治療を適切に組み合わせた「マルチモーダル治療」**の確立です。この治療法を受けた患者の割合は、初期では0%でしたが、後期では58%まで増加しました。
驚異的な生存率の改善
5年生存率の大幅向上
研究結果では、5年生存率が時代とともに劇的に改善していることが示されました:
- 初期(1980-1999年): 68%
- 中期(2000-2010年): 85%
- 後期(2010-2023年): 93%
死亡リスクの大幅減少
死亡リスクについても、治療法の進歩とともに顕著な改善が見られました:
- 中期は初期と比べて71%低下
- 後期は中期と比べて55%低下
- 後期は初期と比べて87%も低下
患者さんにもたらされる希望
個別化医療の実現
この研究成果は、CTEPHが「治療困難な難病」から「コントロール可能な疾患」へと変化していることを示しています。今後は、どの患者さんにどの治療法が最適かを明確にし、より精密な個別化医療の実現が期待されています。
治療選択肢の拡大
現在、患者さんは以下のような治療選択肢から、最適な組み合わせを選択できるようになっています
- 外科的治療: 肺動脈血栓内膜摘除術(PEA)
- カテーテル治療: バルーン肺動脈形成術(BPA)
- 薬物治療: 抗凝固薬、肺血管拡張薬(リオシグアト、セレキシパグなど)
今後の展望
この研究は、指定難病であるCTEPHにおいて、治療法の進歩が患者さんの長期生命予後を大幅に改善させることを科学的に証明しました1。European Respiratory Journalに掲載されたこの研究成果は、世界的にも注目される重要な発見となっています。
今後は、さらなる治療法の最適化と個別化医療の発展により、より多くの患者さんが希望を持って治療に臨めるようになることが期待されます。この画期的な研究結果は、難病と闘う患者さんとご家族にとって、大きな励みとなる素晴らしいニュースといえるでしょう。