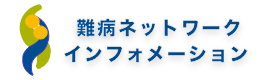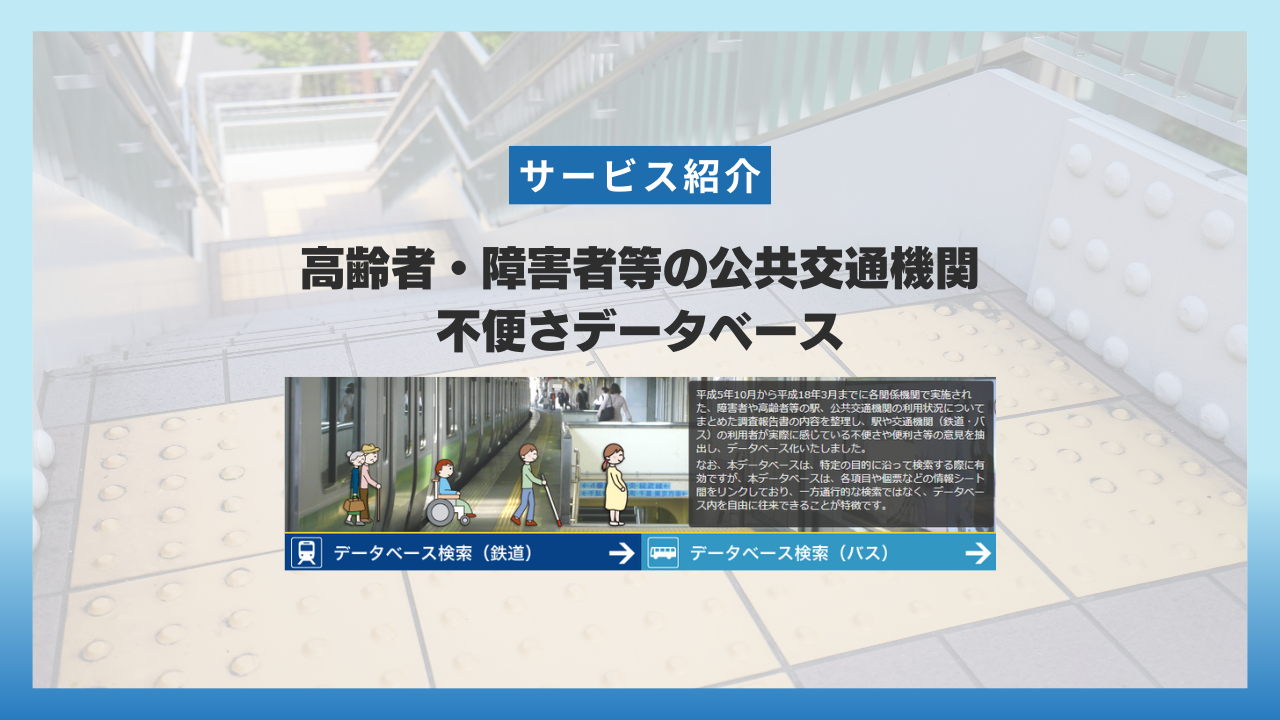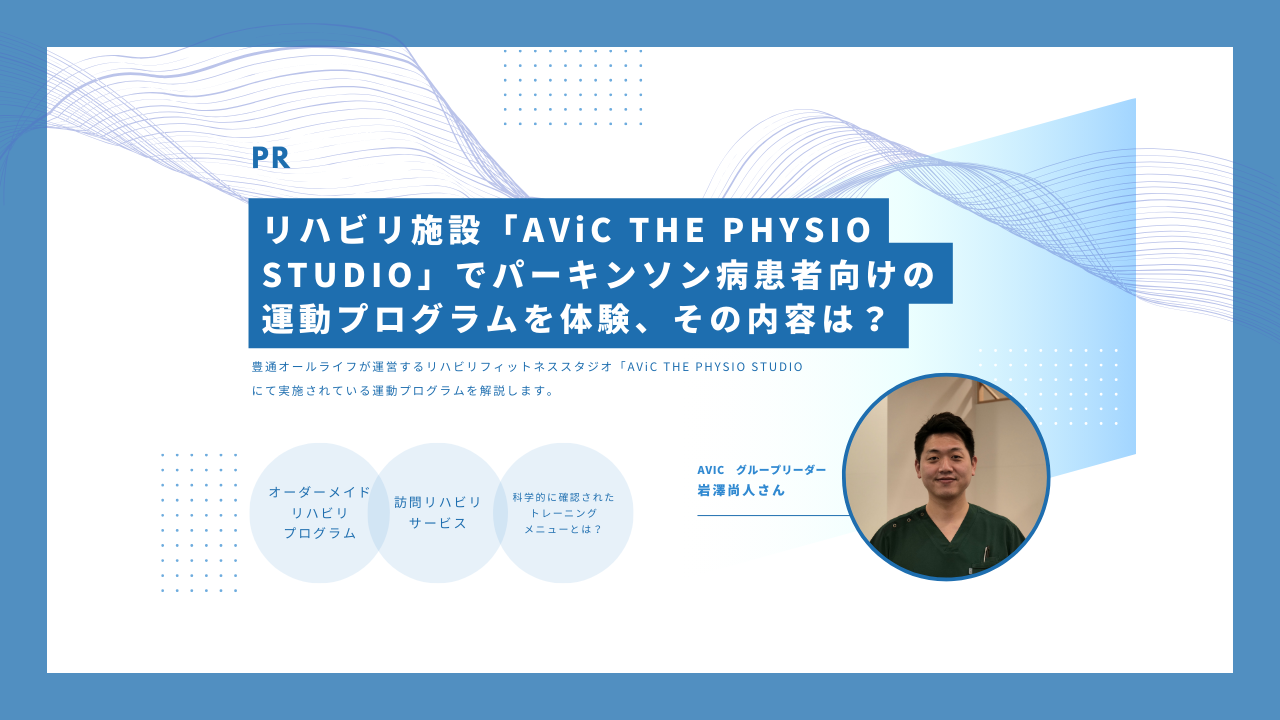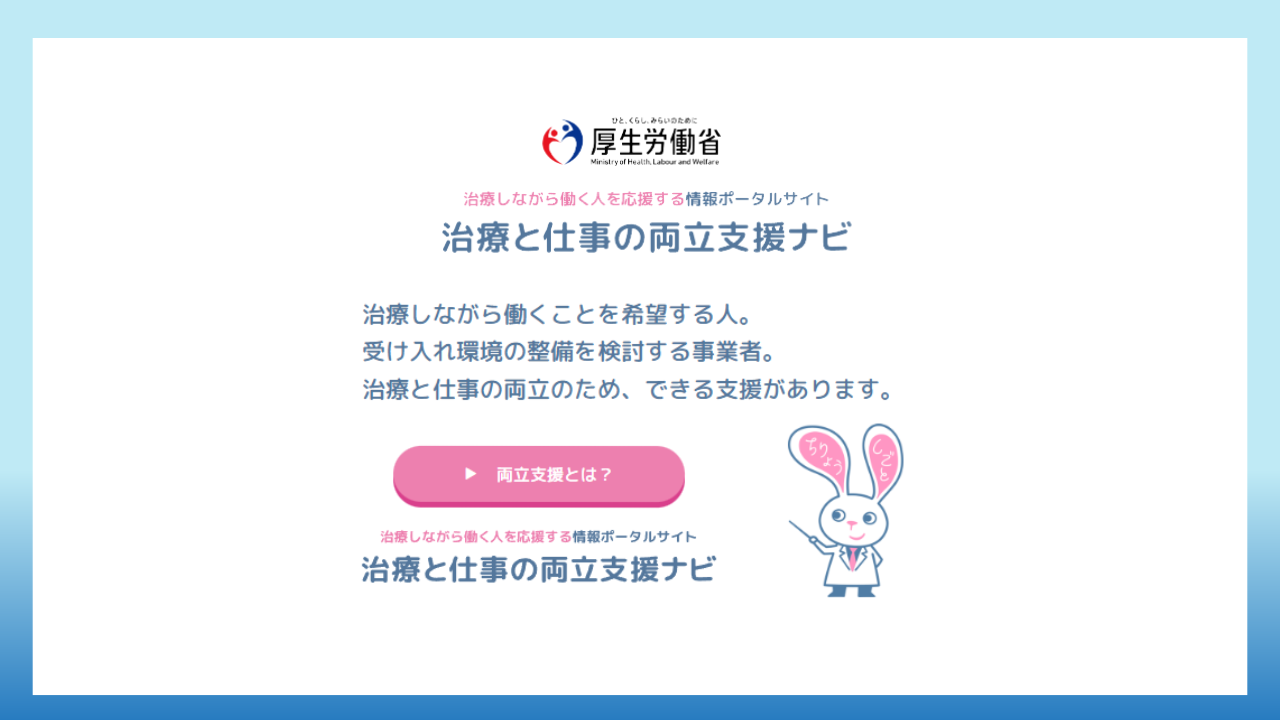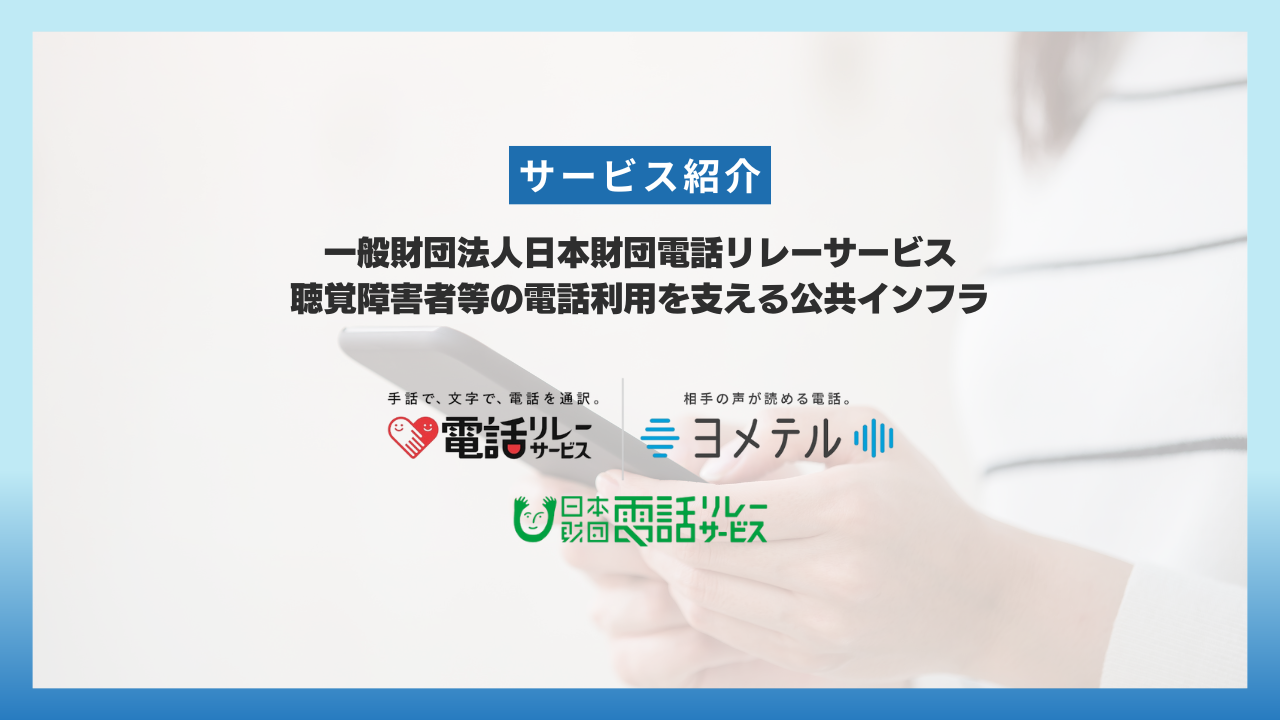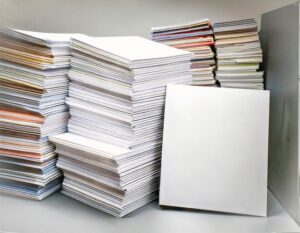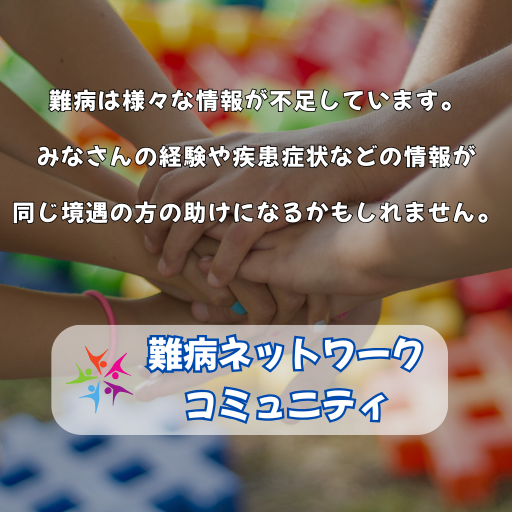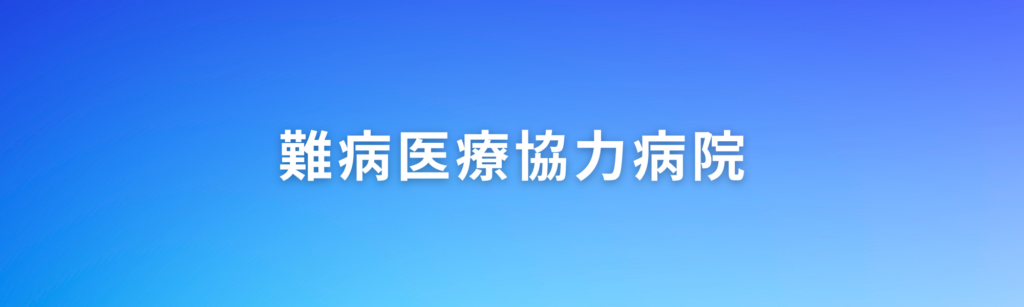慢性血栓塞栓性肺高血圧症とは?
「慢性血栓塞栓性肺高血圧症」は、肺の血管が狭くなることで酸素の吸収が難しくなる、国の指定する「希少難病」の一つです。具体的には、肺動脈に血栓(血の塊)ができてしまうことが原因で、血管が細くなり、呼吸が苦しくなったり、疲れやすくなったりといった症状が現れます。全国に約5,000人ほどの患者さんがいらっしゃるとされています。
希少難病の治療薬開発の課題と九州大学の取り組み
患者さんの数が少ない「希少難病」は、新しい治療薬の開発や、既存の薬の有効性を確認するための臨床研究が難しいという課題があります。しかし、この慢性血栓塞栓性肺高血圧症に対して、九州大学大学院医学研究院の阿部弘太郎教授の研究グループは、国内の10の大学、国、そして製薬会社など、多くの機関と協力して研究を進めてきました。
新たな治療薬「エドキサバン」の有効性と安全性
この共同研究の結果、これまで慢性血栓塞栓性肺高血圧症の治療薬としては認められていなかった「エドキサバン」という薬の有効性と安全性が確認されました。エドキサバンは、以前から他の血栓症の治療薬としては有効性が確認されていた薬です。この研究成果を受け、今年の2月には国がこの病気の治療薬として正式に承認しました。
エドキサバンの特徴の一つは、食事の制限が少ないため、患者さんの負担を軽減できる点です。これは、日々の生活を送る上で患者さんにとって大きなメリットとなります。
産官学連携が拓く希少疾患治療の未来
今回のプロジェクトに参加した九州大学病院の細川和也准教授は、「産官学(産業界、官公庁、学術機関)の多くの組織が協力してプロジェクトを成功させた」と述べています。そして、「これを機会にほかの希少疾患でもデータを創出して、適用を広げる取り組みをしていきたい」と、今後の展望を語っています。
今回の「慢性血栓塞栓性肺高血圧症」に対する新たな治療薬の承認は、患者さんにとって希望の光となるだけでなく、希少難病全体の治療研究に弾みをつける重要な一歩と言えるでしょう。
ソースURL: https://www3.nhk.or.jp/fukuoka-news/20250523/5010028279.html