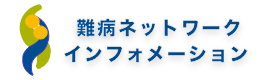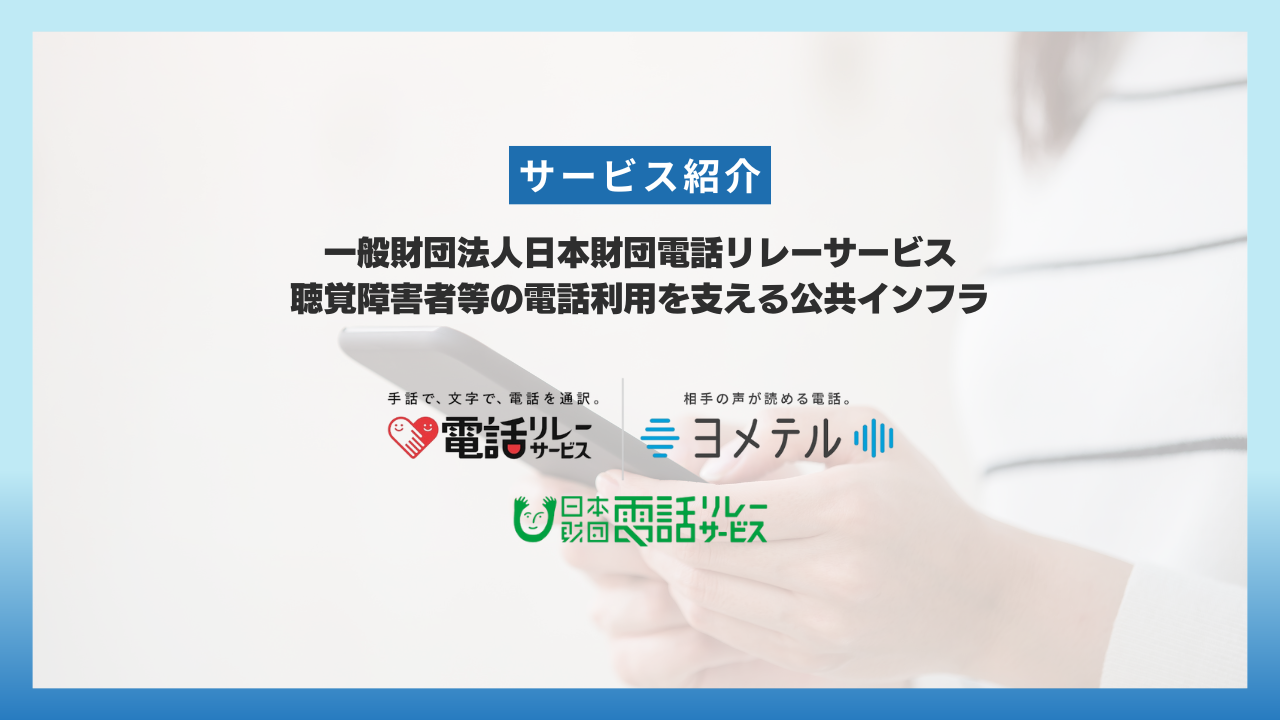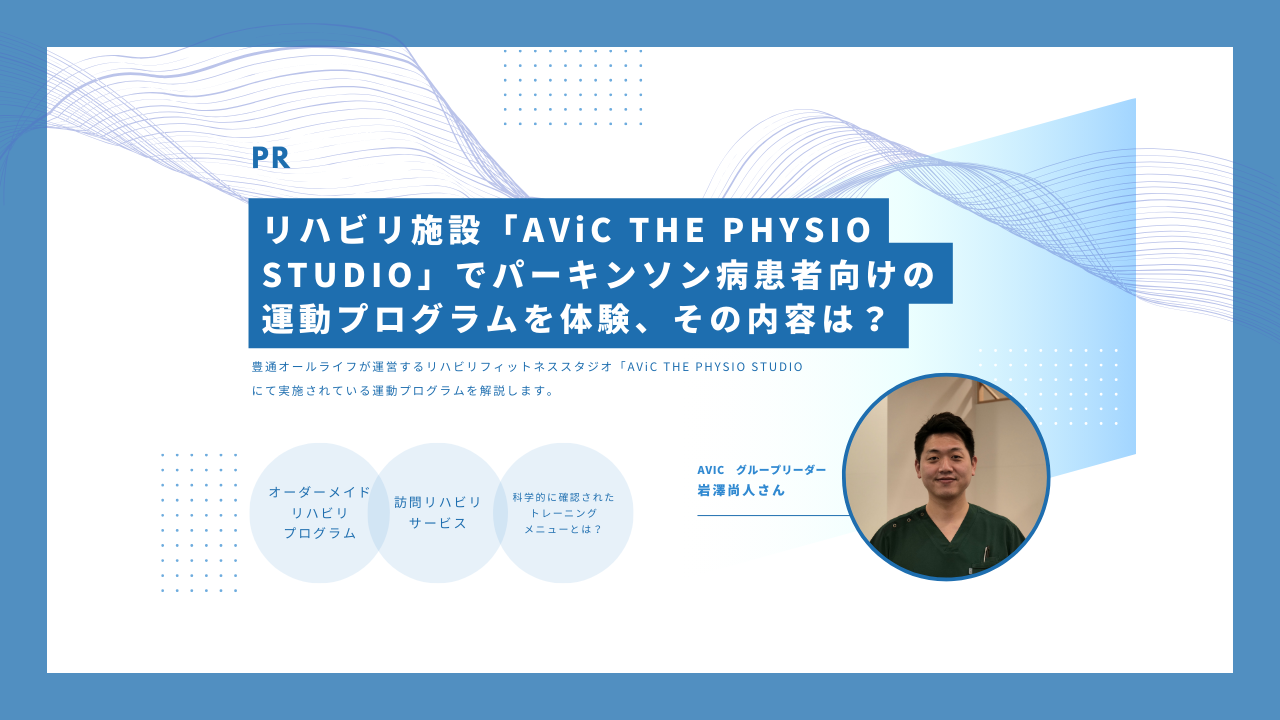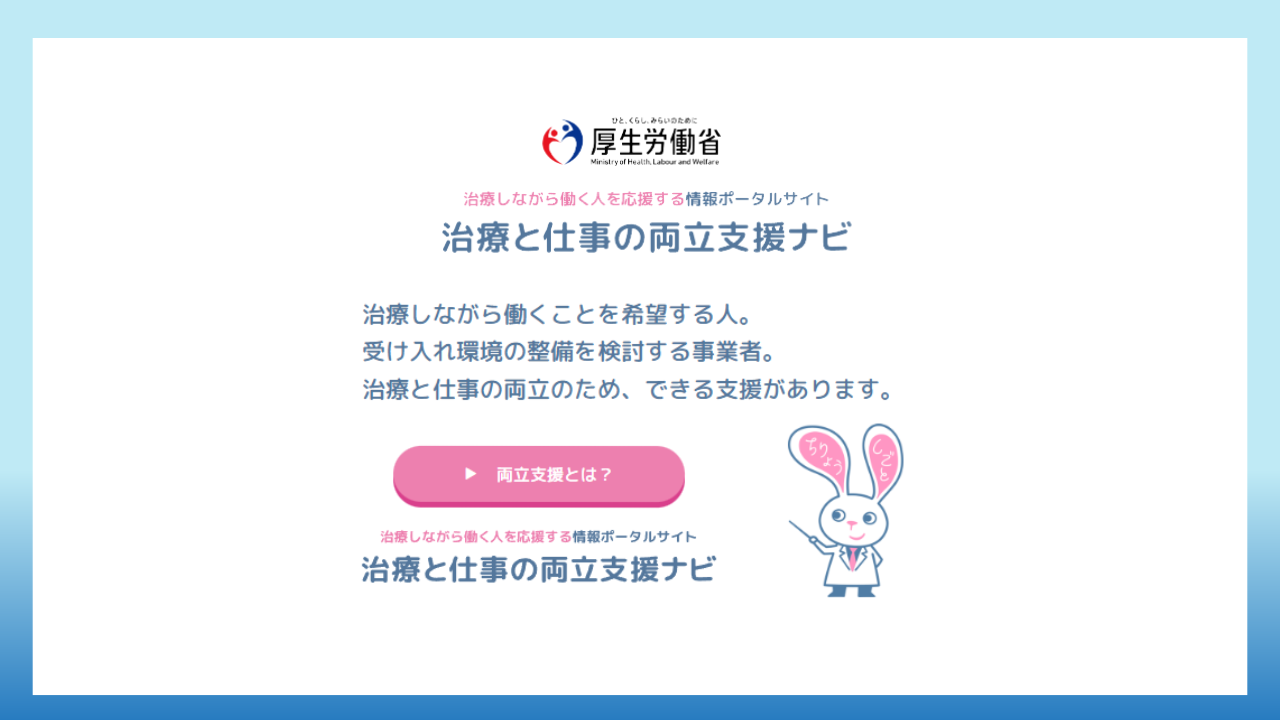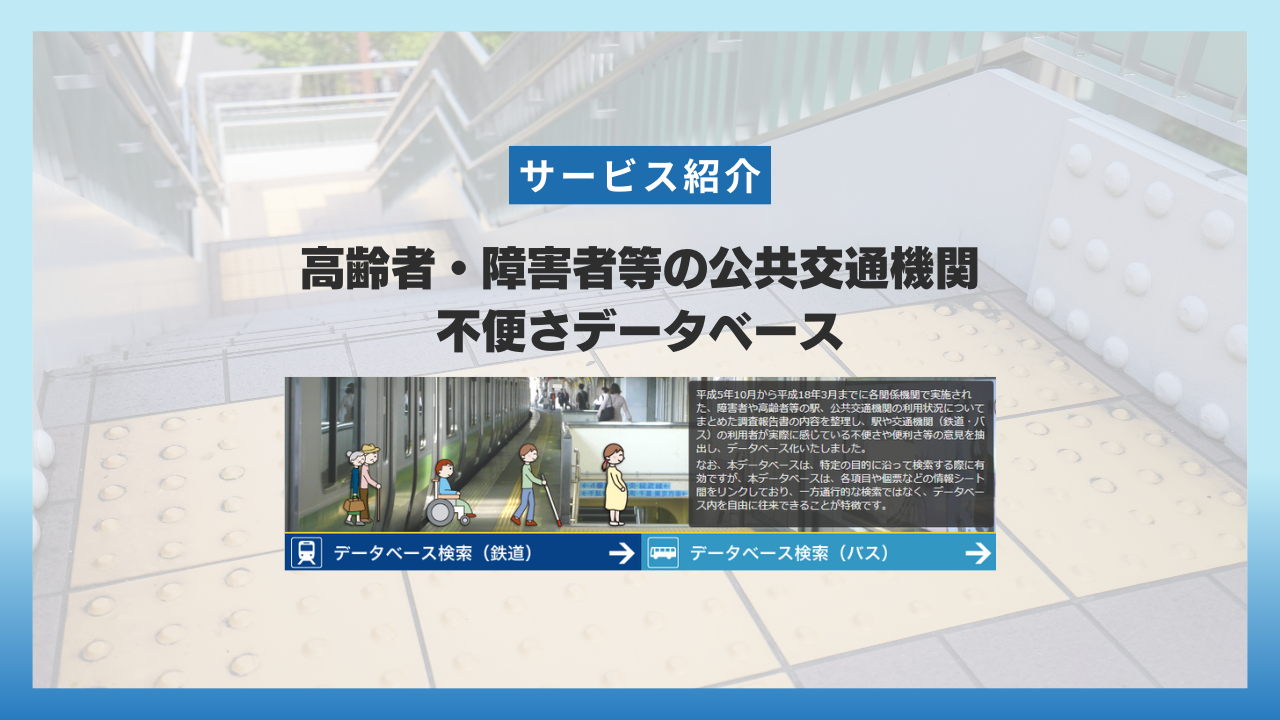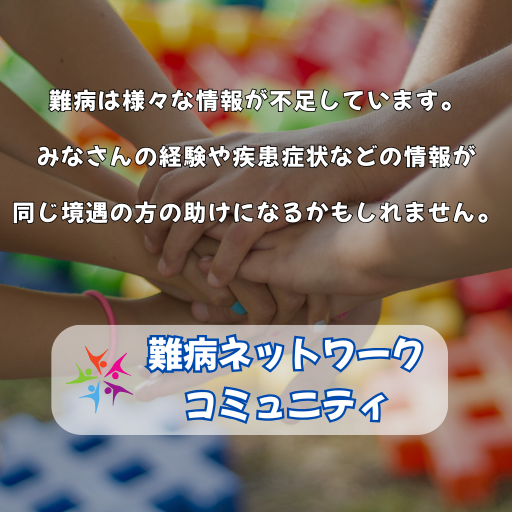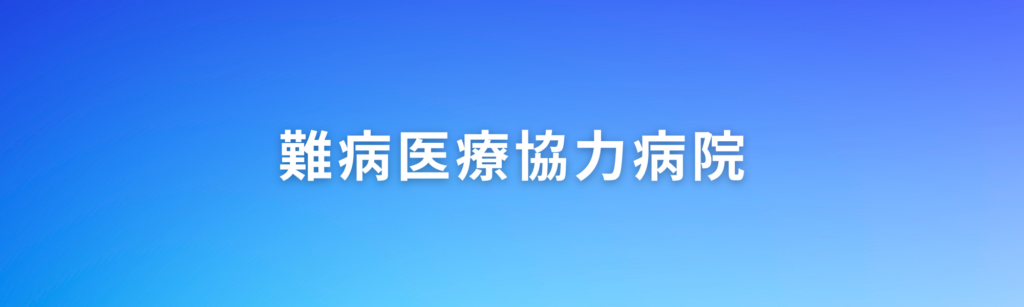潰瘍性大腸炎、発症の約5年前から血液検査で予測可能に
東北大学の研究グループは、難病である潰瘍性大腸炎の発症を、血液検査によって約5年前から高い精度で予測できることを日本人約8万人を対象とした大規模研究で初めて明らかにしました。
研究の概要と方法
研究は、東北メディカル・メガバンク計画によって収集された約8万人分の血液や生活習慣データを解析して行われました。潰瘍性大腸炎を発症した人の発症前の血液を調べたところ、抗EPCR抗体と抗インテグリンαvβ6抗体という2種類の自己抗体が、発症の約5年前から高い割合で陽性となっていることが分かりました。
具体的には、発症前の集団で抗インテグリンαvβ6抗体は52.5%、抗EPCR抗体は51.4%が陽性で、健常者ではほとんど認められませんでした。この2つの抗体を組み合わせることで、さらに高い精度で発症リスクを予測できることも示されました。
生活習慣との関連
また、生活習慣の解析からは「不眠」が潰瘍性大腸炎発症のリスク因子となることも明らかになりました。これは、慢性的な不眠が潰瘍性大腸炎の再燃リスクを高めることとも関連しています。
今後の展望
これらの自己抗体の測定によって、潰瘍性大腸炎の発症リスクを早期に把握し、発症予防や早期発見につなげることが期待されます。東北大学の角田洋一医師は「血液を調べることで、潰瘍性大腸炎になるかどうかを高い確率で予測できることが分かった。将来的には生活習慣の改善や薬を早く飲むことで、患者の数を減らすことができる可能性がある」と述べています。
ソースURL: https://www3.nhk.or.jp/tohoku-news/20250522/6000031393.html