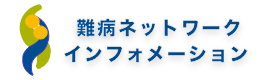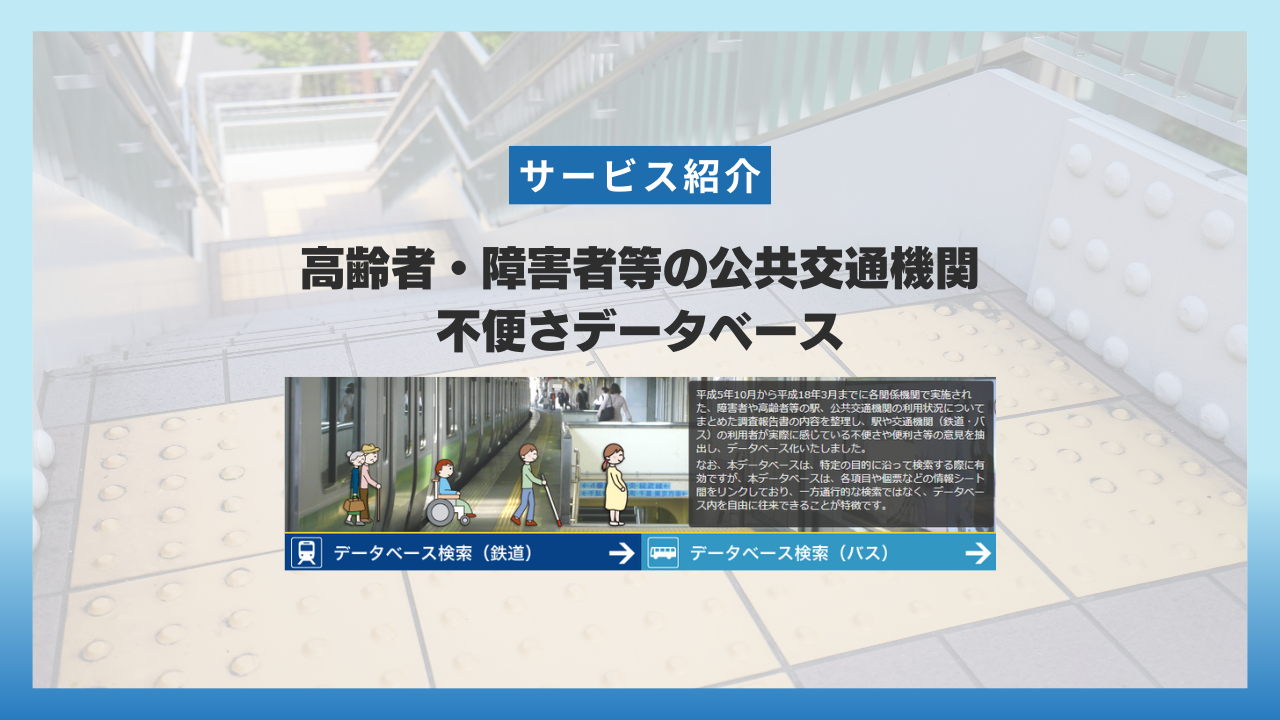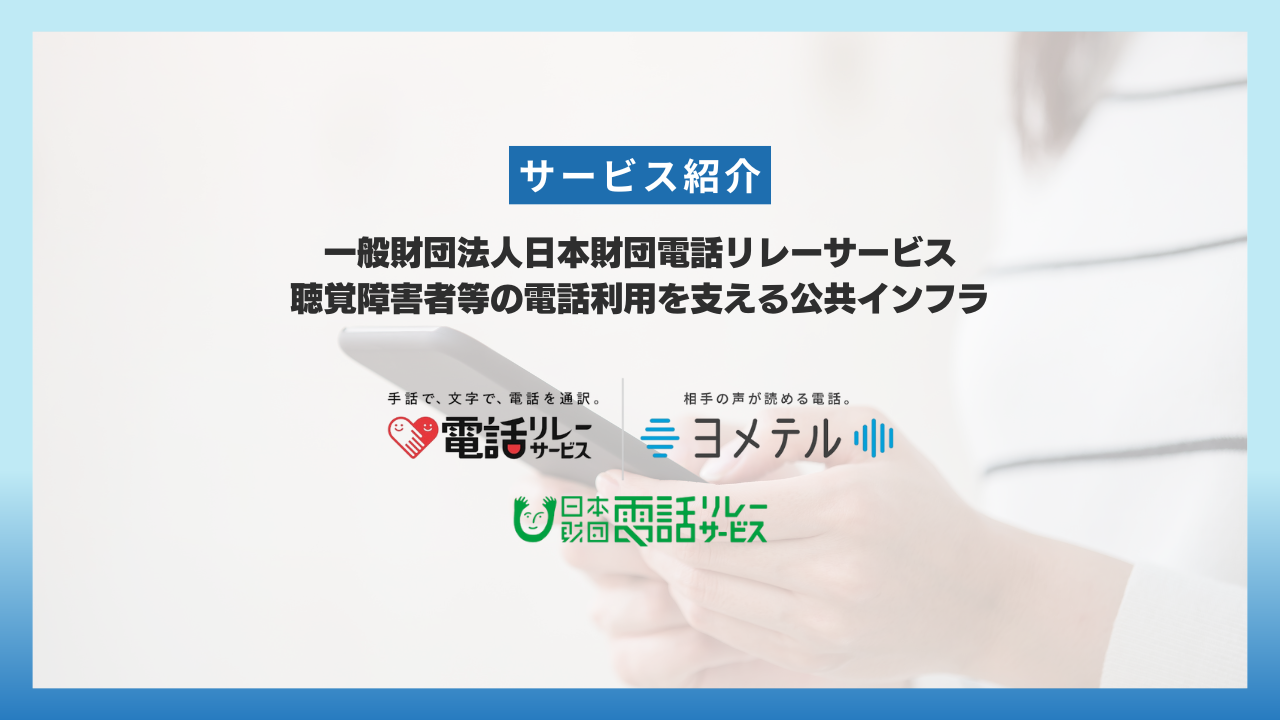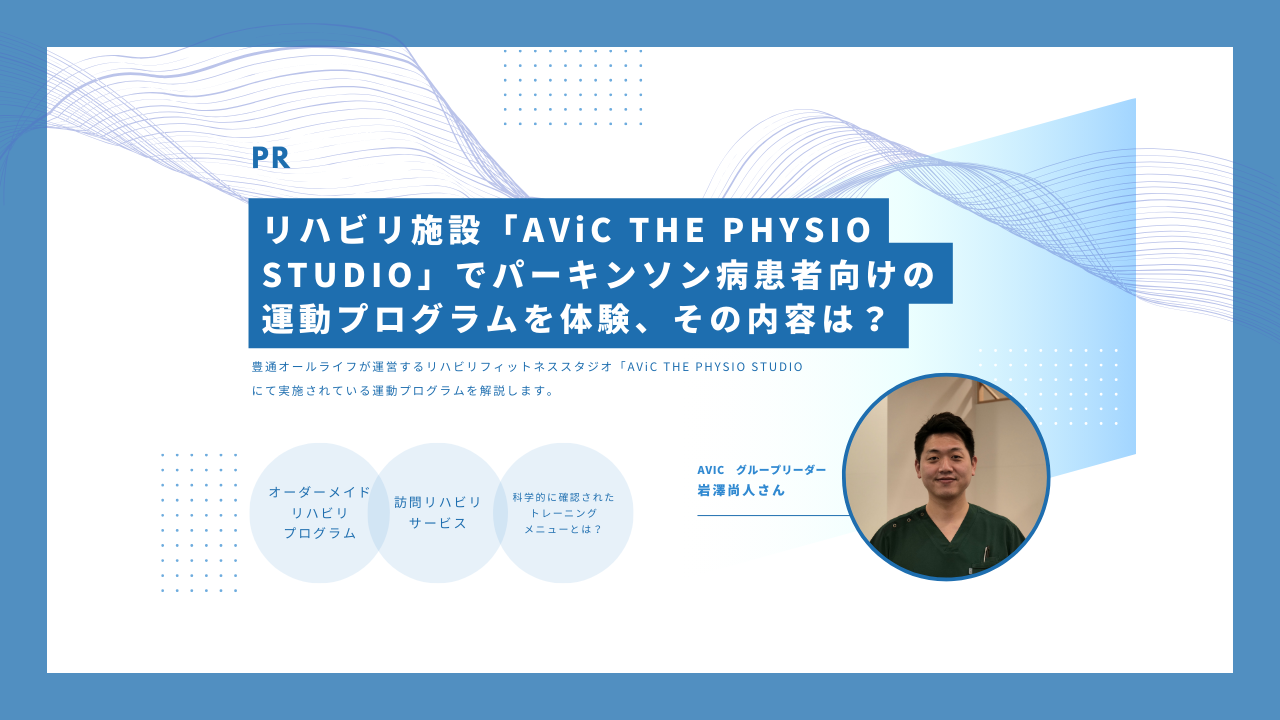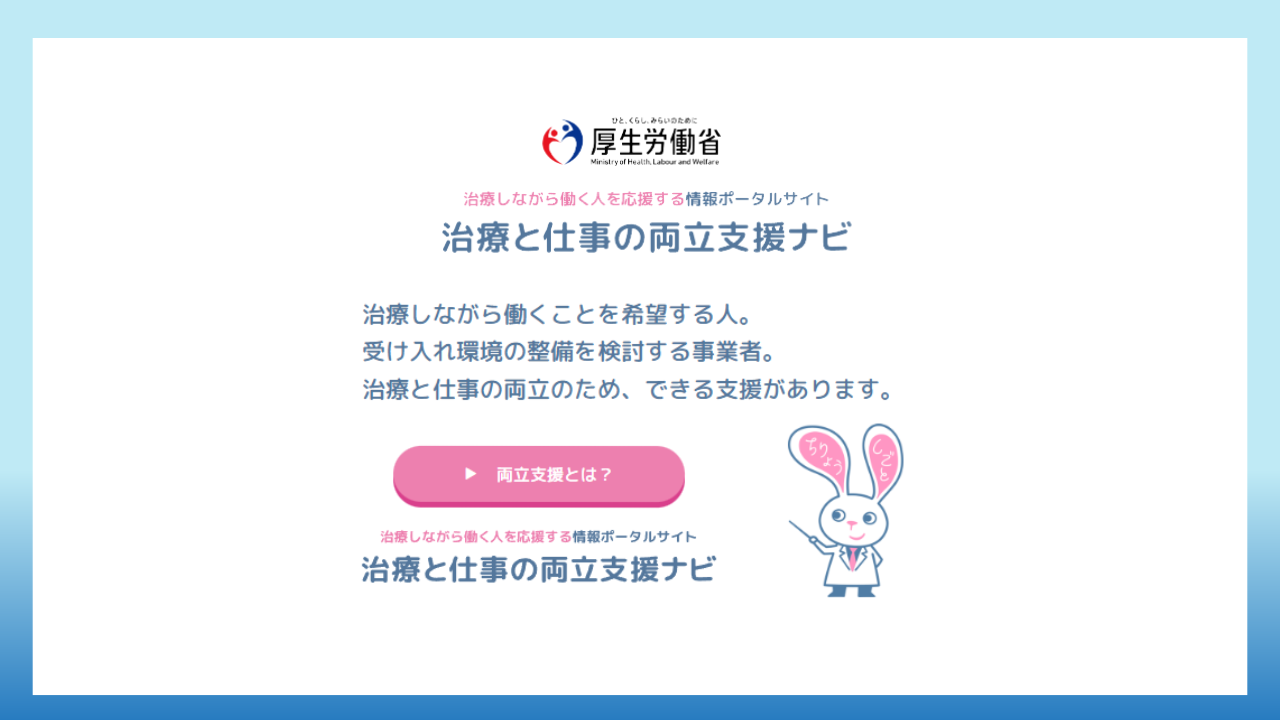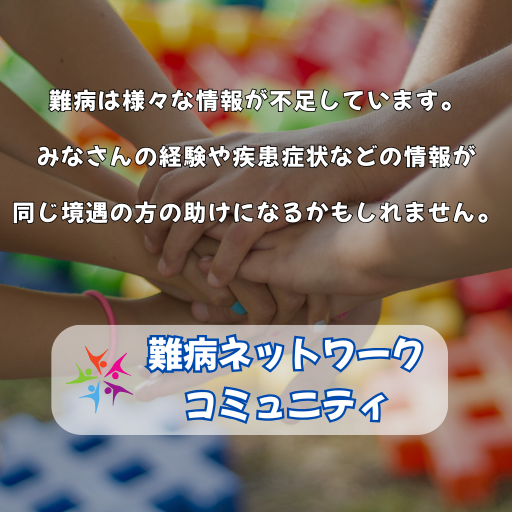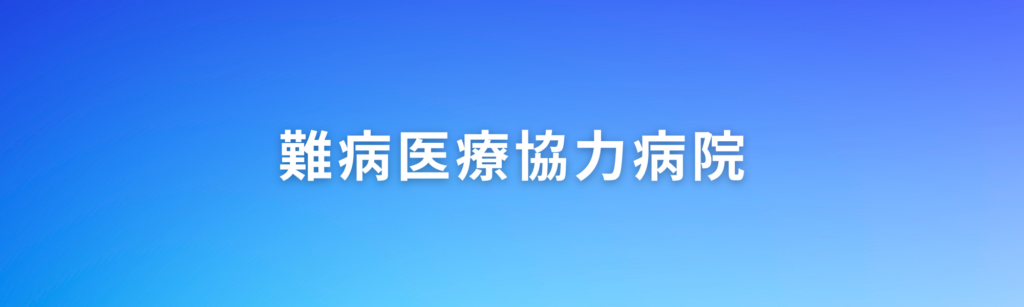関西医科大学の研究チームは2025年3月31日、原因不明で多くの人々を苦しめている「コロナ後遺症」が、指定難病である自己免疫疾患「全身性エリテマトーデス(SLE)」と非常によく似た病態を持つ可能性があるという、研究結果を発表しました。この発見は、確立した治療法がなかったコロナ後遺症に対し、既存の治療薬が有効である可能性を示唆するもので、患者にとって大きな希望の光となるかもしれません。
なぜ続く?コロナ後遺症の謎
新型コロナウイルス感染症が治った後も、倦怠感、呼吸困難、集中力の低下、脱毛といった多様な症状が数カ月から1年以上も続く「コロナ後遺症」。パンデミックが落ち着いた今なお、世界中の多くの人々が以前のような日常生活に戻れず、苦しんでいます。しかし、その根本的な原因は不明で、確固たる治療法も見つかっていないのが現状でした。
研究が突き止めた驚くべき類似点
関西医科大学の研究チームは、コロナ後遺症患者39人の血液を詳しく分析しました。その結果、驚くべき事実が次々と明らかになりました。
体内で続く「免疫の暴走」
コロナ後遺症患者の血液中では、「インターフェロン」という免疫システムがウイルスなどと戦う際に放出するタンパク質が、異常に高いレベルで活動し続けていることが分かりました。これは、体が常に戦闘モードにあるような状態で、全身の不調につながっていると考えられます。
難病「SLE」と同じサインを発見
さらに決定的だったのは、指定難病「全身性エリテマトーデス(SLE)」の診断に用いられる「抗核抗体」という特殊な物質が、調査したコロナ後遺症患者の全員から見つかったことです。SLEは、免疫システムが誤って自分自身の体を攻撃してしまう自己免疫疾患の代表例です。このことから、コロナ後遺症も免疫の異常が関わる自己免疫疾患の一種、特にSLEに酷似した病態である可能性が強く示唆されました。
既存薬が治療の鍵になる可能性
この発見がもたらす最大の希望は、治療法への新たな道筋です。もしコロナ後遺症がSLEと似ているのであれば、すでにSLEの治療に使われている薬が、コロナ後遺症にも効果を発揮する可能性が出てきます。
研究チームは特に、免疫の過剰な働きを抑える作用が報告されている「ヒドロキシクロロキン」というSLE治療薬に注目しており、コロナ後遺症の治療に応用できるかもしれないとしています。
今後の展望
今回の研究は、コロナ後遺症の正体に迫り、その診断や治療法を確立するための極めて重要な一歩です。今後は、血液中の抗体を測定することがコロナ後遺症の確定診断に役立つかどうかが検証され、既存薬を使った治療法の開発が期待されます。原因不明の不調に苦しんできた多くの患者にとって、この研究成果は未来を照らす大きな希望と言えるでしょう。
ソースURL: https://www.kmu.ac.jp/news/laaes7000000vi23-att/20250331Press_Release.pdf