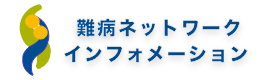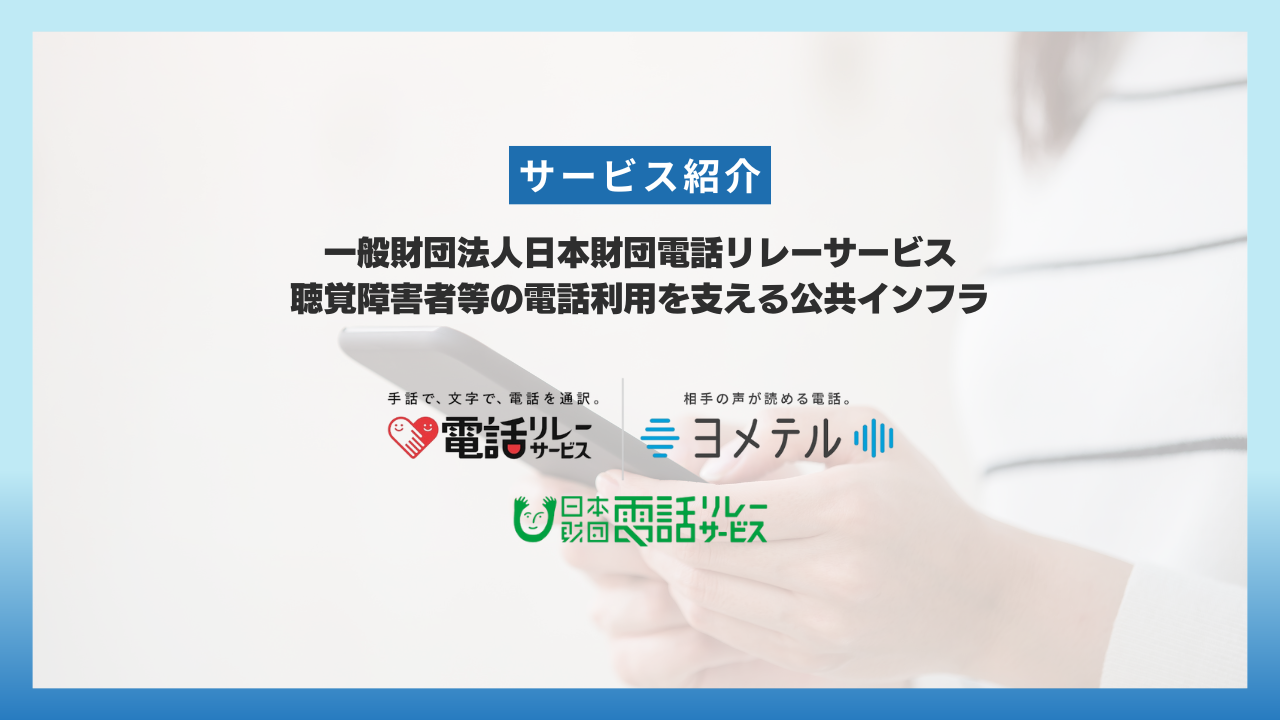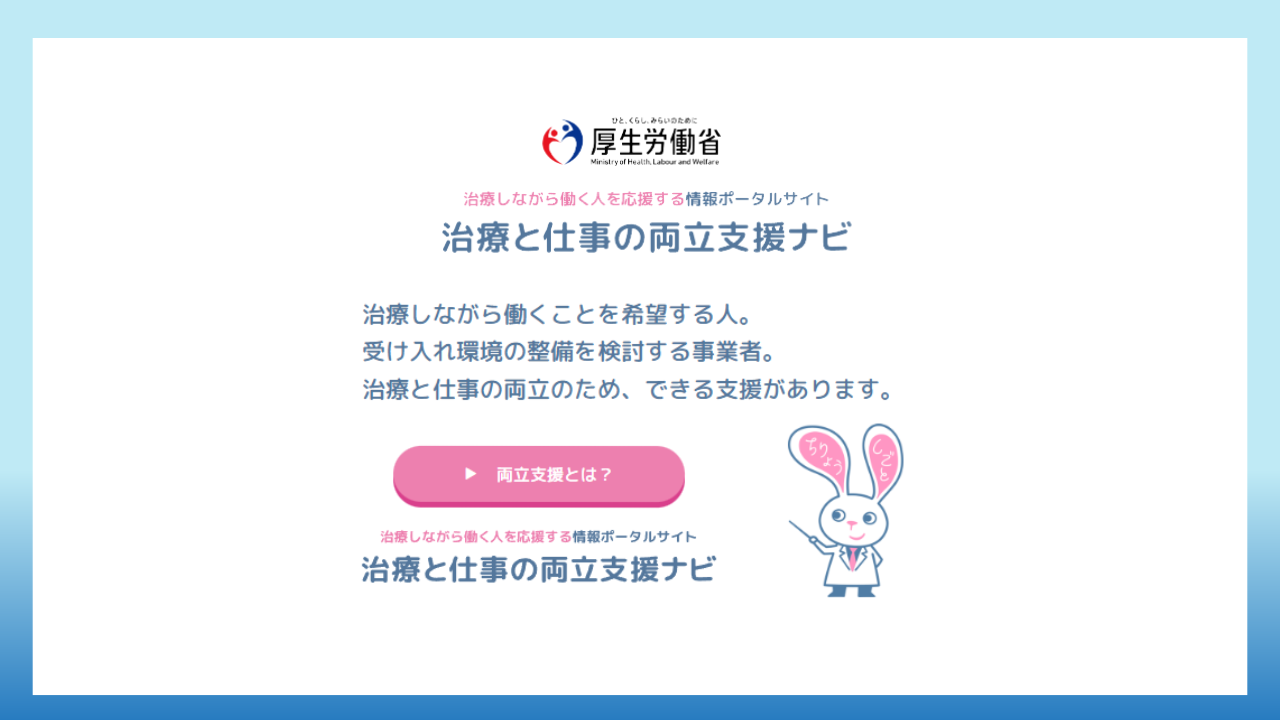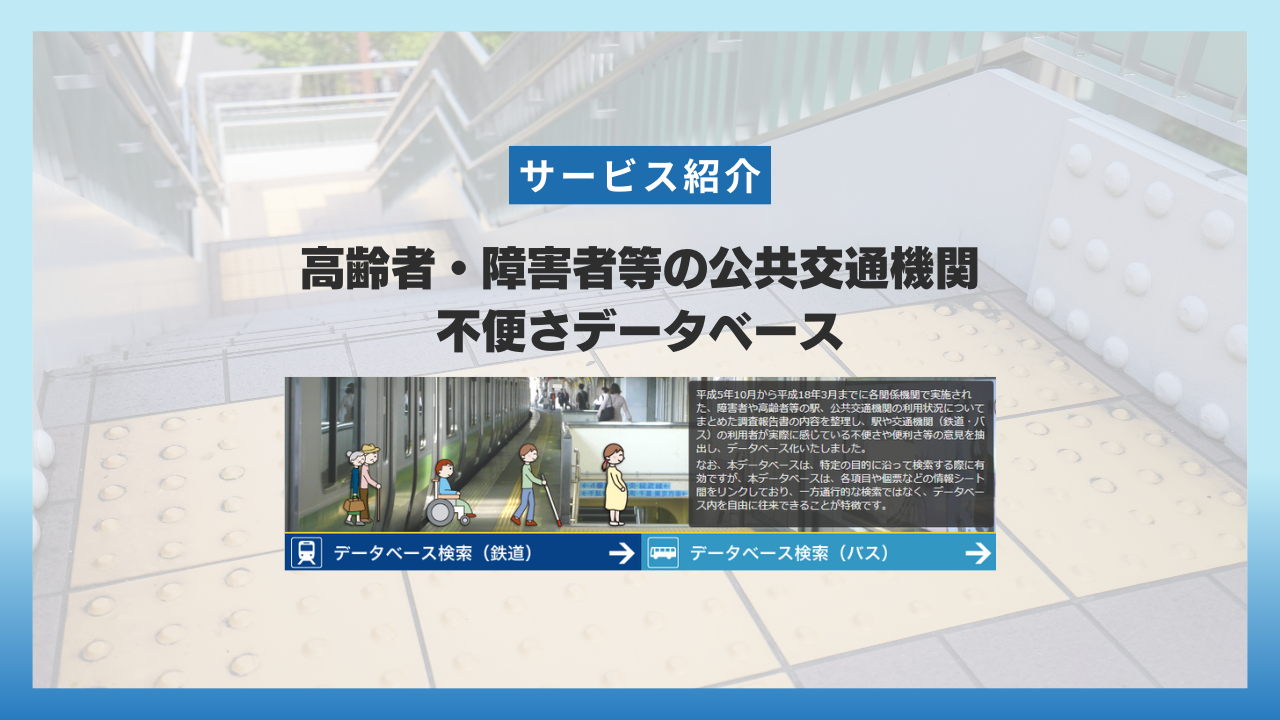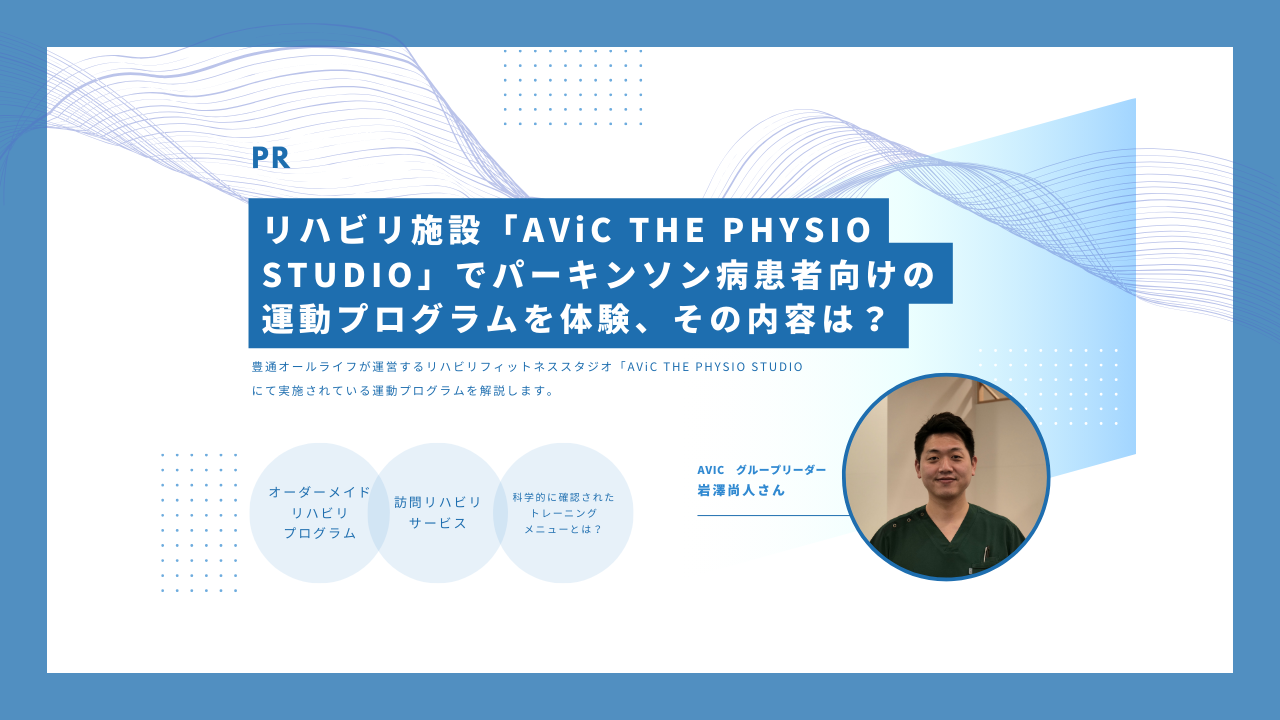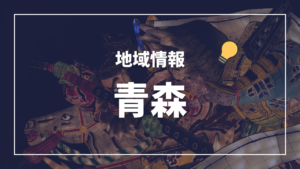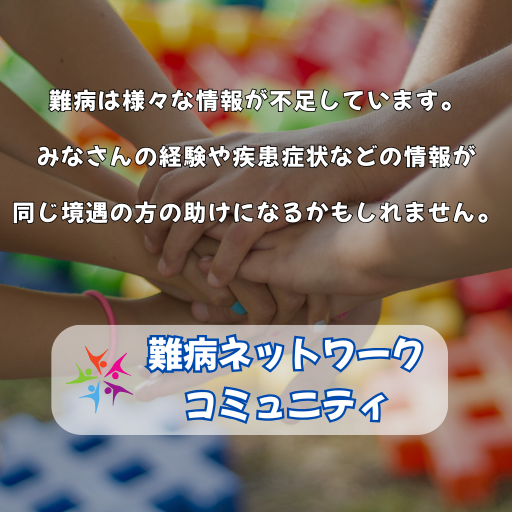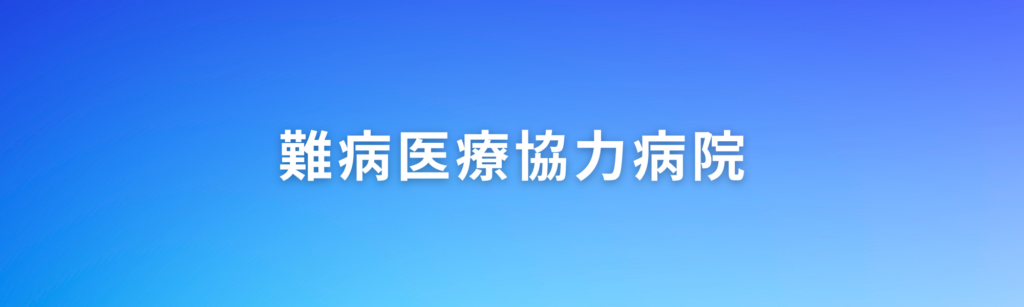日本腎臓病協会と協和キリン株式会社は2025年7月25日、成人の5人に1人にあたる約2,000万人が罹患していると推定される「慢性腎臓病(CKD)」について、その認知度が42.6%にとどまるという衝撃的な調査結果を発表しました。この調査は、自覚症状が乏しいまま静かに進行するCKDのリスクが、いまだ社会に広く浸透していない現状を浮き彫りにしています。
「静かなる病気」慢性腎臓病(CKD)とは
慢性腎臓病(CKD)は、腎臓の働きが徐々に低下していく様々な腎臓病の総称です。恐ろしいのは、初期段階では自覚症状がほとんどないことです。しかし、放置すれば脳卒中や心臓病のリスクを高め、最終的には人工透析や腎移植が必要になることもあります。日本の成人における患者数は約2,000万人と推定されており、誰にとっても他人事ではない国民病の一つです。
調査でわかった認知度のリアルな現状
20代から70代の一般市民1,625名を対象に行われた今回のインターネット調査では、CKDに対する意識の低さが明らかになりました。
- 低い認知度: CKDを「症状も含めてよく知っている」または「病名だけは知っている」と回答した人は、全体の42.6%でした。
- 内容の理解不足: 「症状を含めてよく知っている」と深く理解している人は、わずか6.6%に過ぎませんでした。
- 年代による差: 認知度は年齢層が上がるにつれて高くなる傾向にありましたが、30代は50代と同程度の認知度を示すという特徴も見られました。
- 健診の壁: 健康診断や人間ドックを定期的に受けない理由として最も多かったのは「費用がかかるから」(34.2%)で、特に働き盛りの30代(42.7%)と40代(44.2%)でその傾向が顕著でした。
専門家が警鐘「早期発見こそが何より重要」
この結果を受け、日本腎臓病協会理事長の柏原直樹医師は、特に勤労世代への啓発の重要性を強調しています。
CKDは自覚症状が乏しいために軽視されがちですが、早期に発見すれば回復も期待できます。柏原医師は、「健康診断における尿蛋白やeGFR(推算糸球体ろ過量)の値にもっと注意を向けてもらうよう、継続した啓発活動が重要です」と述べ、定期的な健診による早期発見を強く呼びかけています。
今回の調査結果は、多くの人が気づかないうちに進行するCKDのリスクと、その対策の重要性を改めて社会に突きつけるものとなりました。日本腎臓病協会と協和キリンは今後も連携し、疾患啓発活動を続けていく方針とのことです。
ソースURL: https://www.kyowakirin.co.jp/pressroom/news_releases/2025/pdf/20250725_01.pdf