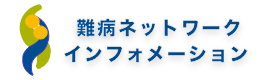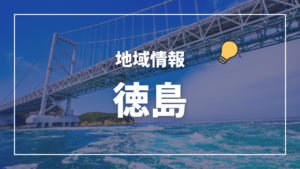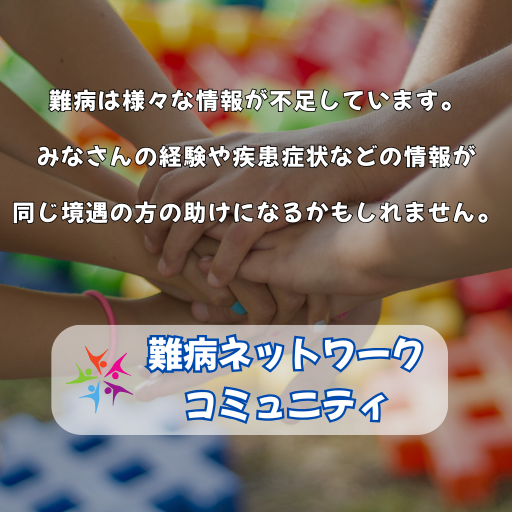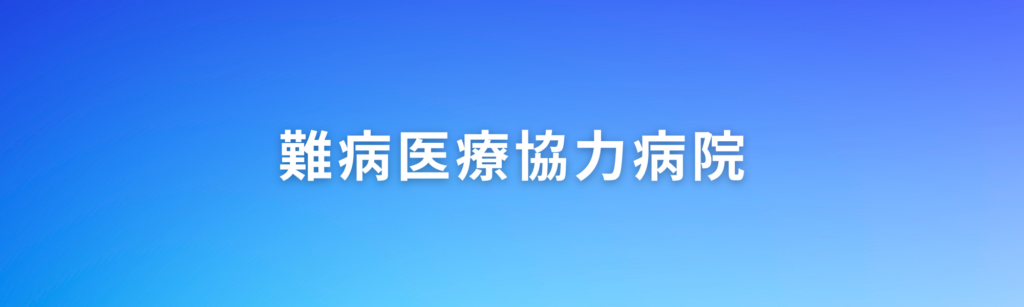治療法が限られ、予後不良とされる難病「特発性肺線維症(IPF)」の患者さんにとって、大きな希望となる画期的な研究成果が発表されました。東京慈恵会医科大学、国立がん研究センター、埼玉県立循環器・呼吸器病センターの共同研究グループは2025年7月22日、IPFの進行に関わる新たな治療標的として「PAK2」という酵素を発見したことを明らかにしました。この発見は、これまで根本的な治療法がなかったこの深刻な病気に対する、新しい治療薬開発への道を拓くものです。
肺が硬くなる難病「特発性肺線維症(IPF)」とは
特発性肺線維症(IPF)は、明確な原因がないまま肺が徐々に硬くなり(線維化)、呼吸機能を失っていく進行性の病気です。診断されてからの平均生存期間は約3~5年とされ、非常に予後が悪い指定難病の一つとして知られています。現在の治療法は病気の進行を遅らせることが中心で、根治的な治療法は確立されていませんでした。
最先端技術が解き明かした病気のメカニズム
研究チームは、個々の細胞の遺伝子の働きを詳細に分析する「シングルセルRNA-seq解析」や、組織内での細胞の位置関係まで把握できる「空間トランスクリプトーム解析」といった最先端の技術を駆使しました。
この分析により、以下の重要な事実が突き止められました。
- 病気を悪化させる“悪玉”細胞を発見: IPF患者さんの肺では、線維化を強力に推し進める特殊な線維芽細胞(WNT5A+ CTHRC1+線維芽細胞)が存在することを特定しました。
- 進行を操る“スイッチ”を特定: この“悪玉”細胞やその周辺で、「PAK2」という酵素が活発に働いている(活性化している)ことを発見しました。このPAK2が、病気の進行をコントロールする重要な「スイッチ」の役割を果たしていると考えられます。
新たな治療法への大きな一歩
研究チームは、この「PAK2」の働きを止めることが治療に繋がるのではないかと考え、PAK2阻害剤を用いた実験を行いました。
その結果、マウスを使った実験モデルにおいて、PAK2阻害剤が肺の線維化(硬くなること)を強力に抑制する効果を示しました。これは、PAK2を標的とすることで、IPFの進行を食い止められる可能性を科学的に証明したものです。
今後の展望 - 患者さんの元へ届けるために
今回の研究成果は、IPFの病態解明を大きく前進させ、全く新しいアプローチの治療戦略の可能性を示しました。
研究チームは今後、このPAK2阻害剤を実際の治療薬として患者さんに届けられるよう、慈恵医大発のベンチャー企業などと連携し、製剤開発を進めていくとしています1。この研究が、IPFに苦しむ多くの患者さんとそのご家族にとって、未来を照らす希望の光となることが期待されます。
ソースURL: https://www.ncc.go.jp/jp/information/researchtopics/2025/0722/20250722.pdf