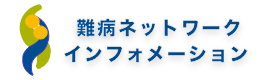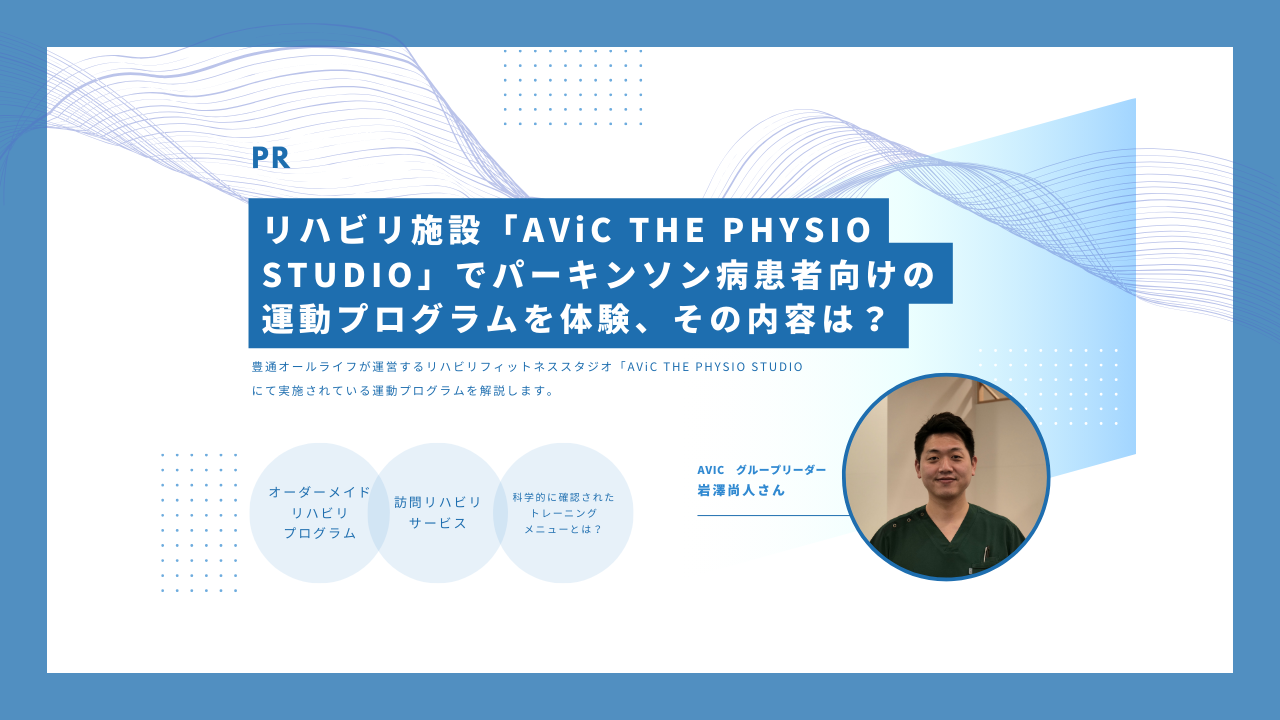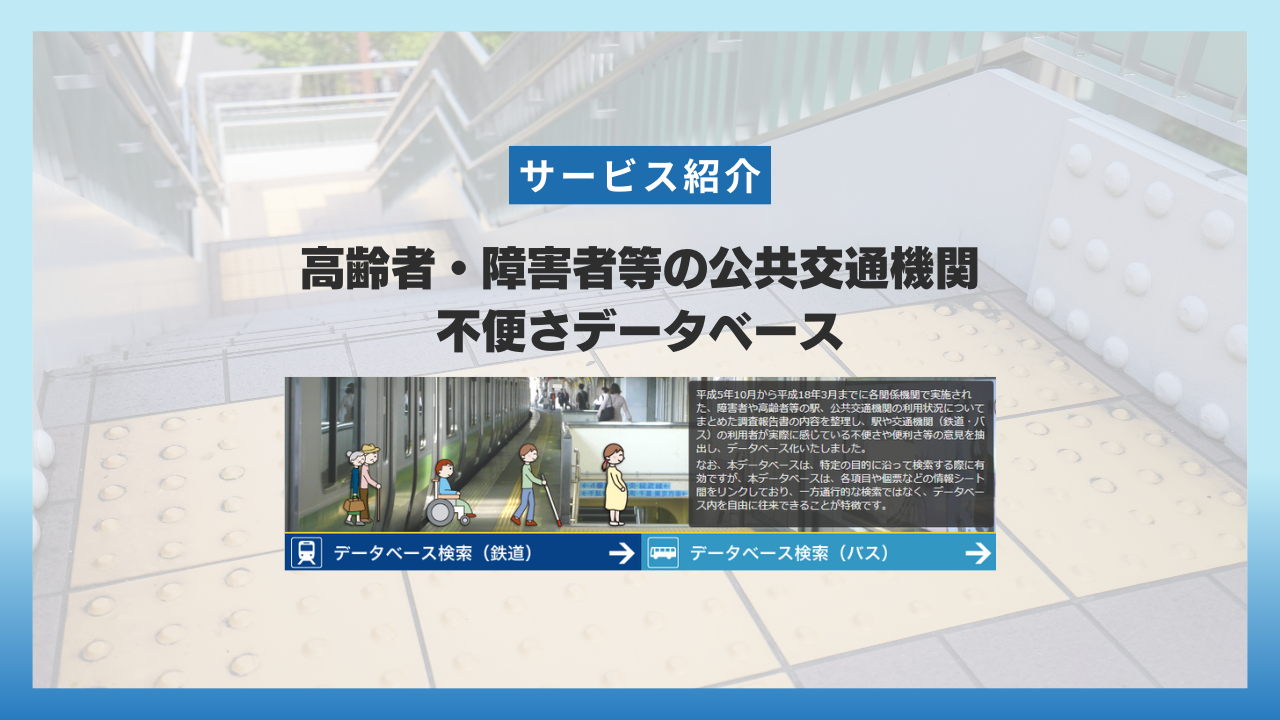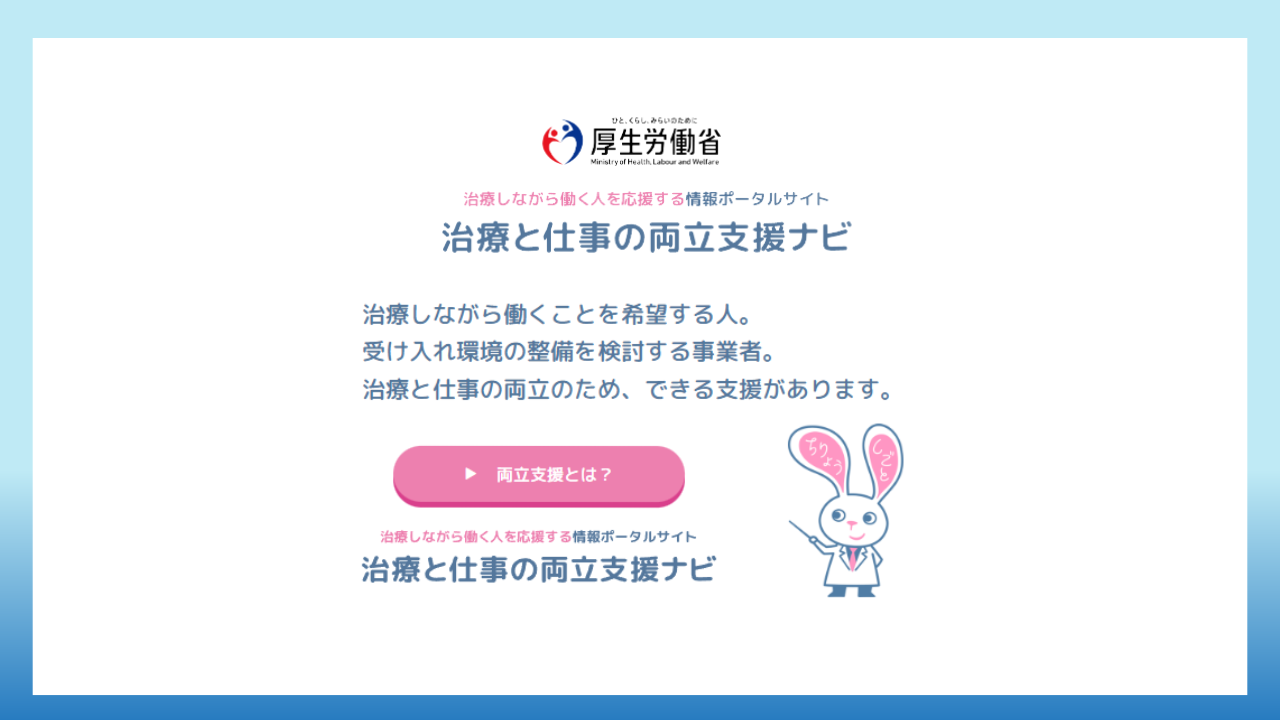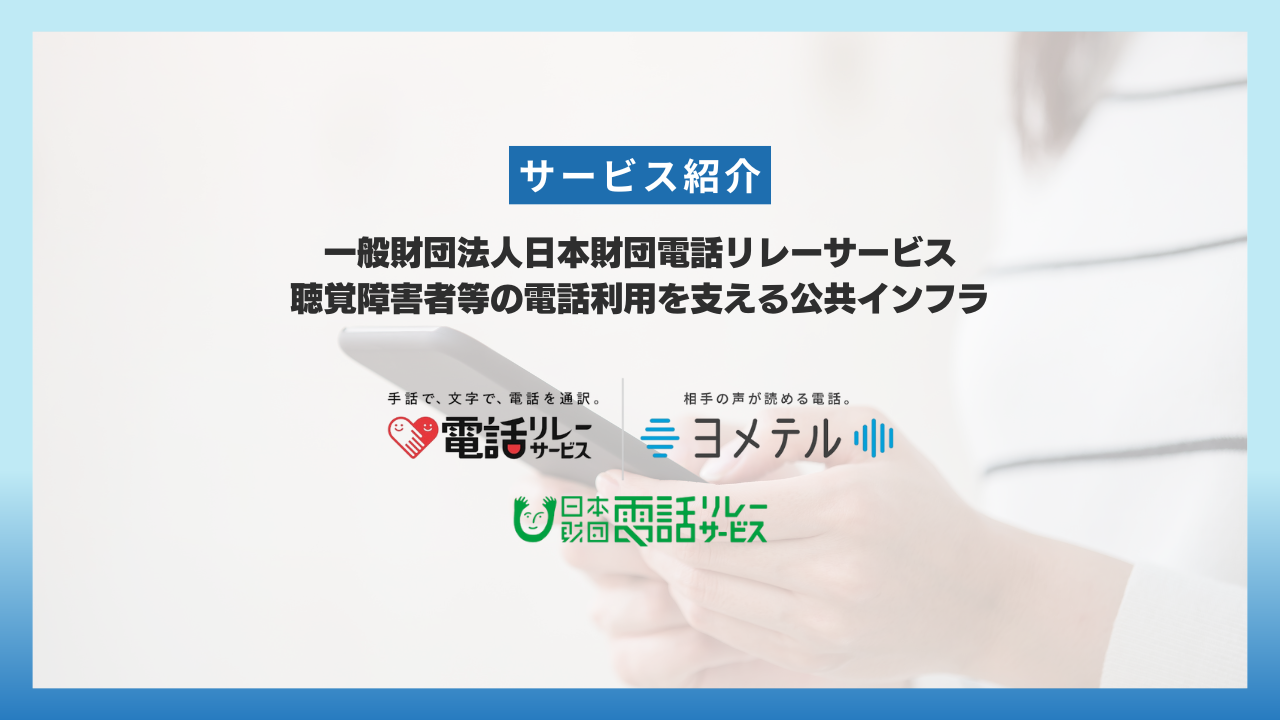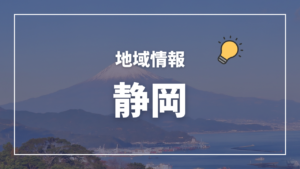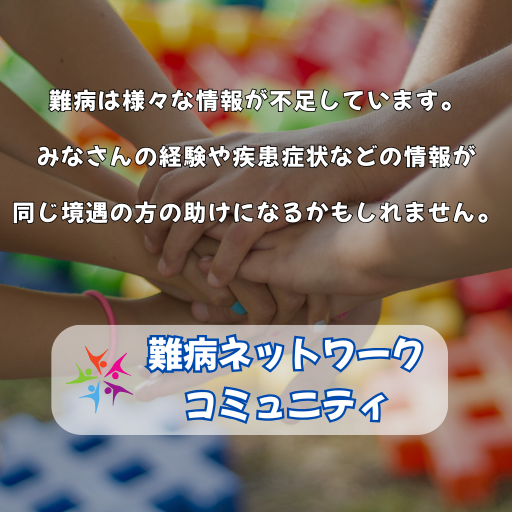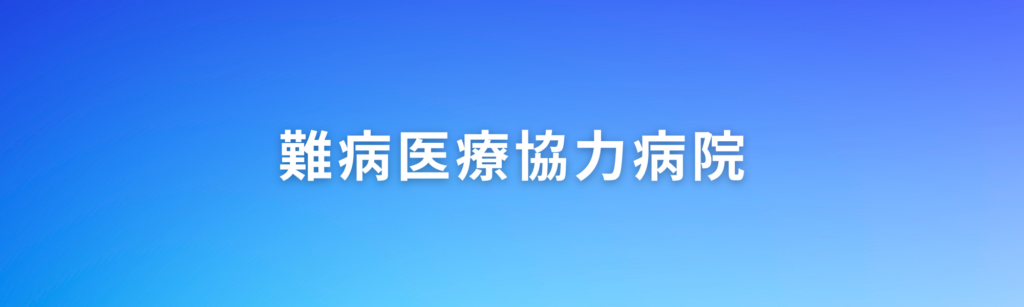2025年3月12日、千葉市にある千葉大亥鼻イノベーションプラザを訪問し、POEMS症候群サポートグループの方々にお話を伺いました。POEMS症候群(クロウ・深瀬症候群)は、全国でわずか約400名と推定される非常に希少な難病です。このような希少疾患では、患者同士の情報共有や医療者との連携が特に重要となります。患者でありながら研究者でもある猪野毛朝飛理事は、患者会と研究者をつなぐ貴重な存在です。また診療ガイドライン編集委員の先生方と、2026年度中のガイドライン完成を目指して取り組んでいます。

左から猪野毛さん、難病ネットワークの恒川、理事長の松尾さん、副理事長の植田さん
POEMS症候群(クロウ・深瀬症候群)について
疾患概要
2015年に指定難病16として指定された疾患です。進行が早い方もおられ、体のさまざまな部分に影響を及ぼします。
POEMS症候群は、以下の名前でも呼ばれています
- Polyneuropathy(多発神経炎), Organomegaly(臓器肥大), Endocrinopathy(内分泌異常), M-protein(Mタンパク産生), Skin changes(皮膚病変)Syndrome(症候群)⇒POEMS
POEMS症候群は、上記の代表的な症状の頭文字を繋げたもので、非常にまれな血液の病気です。 - クロウ・深瀬症候群(Crow-Fukase Syndrome)
- 高月病(Takatsuki Disease)
POEMS症候群は、1の代表的な症状の頭文字を繋げたもので、非常にまれな血液の病気です。
疾患発症のメカニズム
- 骨髄内で形質細胞※1が異常に増殖します。異常に増殖するとPOEMS症候群や多発性骨髄腫などの病気の原因になると考えられています。
- 異常に増殖した形質細胞は、血管内皮細胞増殖因子(VEGF:サイトカイン※2の一種)の産生を促進します。
- POEMS症候群では、血中のVEGFレベルが異常に高くなり、VEGFは血管の透過性を高め、浮腫や胸水、腹水などの症状を引き起こします。
- また、その他の炎症性サイトカインも上昇して末梢神経障害など全身の様々な症状を引き起こしていると考えられています。
※1:形質細胞(Plasma Cell)は、B細胞が成熟して変化した免疫系の細胞であり、主に抗体(免疫グロブリン)を産生する役割を担っています。これらの細胞は、体内に侵入した病原体や異物に対抗するために、特異的な抗体を生成し、免疫応答を助けます。
※2:サイトカインは多様な種類があり、主に免疫系において細胞間のコミュニケーションを担う重要な役割を果たします。これらの分子は、特定の受容体を介して標的細胞に作用し、細胞の増殖、分化、機能の調整を行います。
症状
POEMS症候群の症状は以下のように進行することが多いです。しかし、症状や進行のはやさは患者さんごとに異なります。
- 初期症状:多くの患者は、手や足のしびれや脱力感、痛みなどから始まります。これらの症状は、下肢から始まり、徐々に上肢へと広がることが多いです。
- 進行する神経症状: 症状が進行するにつれて、筋力低下や運動機能の障害が悪化し、最終的には歩行困難になることがあります。進行が速いと1年以内に寝たきりになることもあります。
- 臓器腫大: 肝臓や脾臓、リンパ節などの腫大が見られ、腹部の膨満感や不快感が生じることがあります。臓器腫大は、POEMS症候群の特徴的な症状の一つです。
- 内分泌障害: 糖尿病や甲状腺機能低下症、男性では女性化乳房、女性では月経不順などが現れる方もいます。
- 皮膚変化: 皮膚の色素沈着や体毛の増加(剛毛)、血管腫などの皮膚異常が見られます。
- 浮腫と体液貯留: 手足のむくみや胸水、腹水が見られることがあり、呼吸困難や腹部の不快感が生じることがあります。浮腫は、血管透過性の亢進によって引き起こされます。
早期の診断と治療が重要です。適切な治療を受けられると、10年以上の無再発生存も望めます。
診断
診断には、血液検査によるMタンパクやVEGFの測定が有用ですが、VEGFの検査方法が血清法と血漿法の2種類あります。診断基準では血清法での測定結果で>1000 pg/mLとされています。
参考URL:日本神経治療学会 https://www.jsnt.gr.jp/img/20241112_vegf.pdf
遺伝
一般的に、POEMS症候群は遺伝性ではないと考えられています。
治療
- 自家末梢血幹細胞移植: 血液細胞をつくる造血幹細胞というものを取り出し、高用量化学療法で骨髄を壊した後に移植する方法です。長期の寛解を望める一方、重篤な合併症もあるため、移植に適応がある方は限られています。
- 免疫調整剤: サリドマイド、レナリドミド、ポマリドミド
- プロテアソーム阻害薬: ボルテゾミブ、イキサゾミブ
- 抗体医薬品: エロツズマブ、ダラツムマブ
- 放射線療法: 単一骨病変の治療に用いられます。
※サリドマイド以外は未承認薬となっており、使用には医療機関の倫理審査を通過する必要があります。
日常の管理
- 定期検査: MタンパクやVEGFの測定が再発の基準として有用です。定期的にかかりつけの医療機関を受診し血液検査が必要です。
- リハビリについて: POEMS症候群においてリハビリはQOLの改善に効果的です。
- 合併症の予防: 治療中や治療後は免疫機能が低下することがあるため、感染症に対する予防が必要です。
患者会の歩み
2014年6月に病気の仲間と情報交換を行いたいと考え、現在の理事長である 松尾眞一さんがFacebook上で患者会グループ作り活動を開始して8月にはホームページを開設と精力的に活動し、現在に至っているそうです。当時は全国で340人しか同疾患が見つかっておらず、同じ病気の人と繋がり情報交換を行うのに大変苦労をされたそうです。(現在の患者数 約400名と推定) 理事長ら数名は、厚生科学審議会疾病対策部会第1回指定難病検討委員会の傍聴に参加するなど積極的に活動し、2015年に厚生労働省指定難病(行政病名:クロウ・深瀬症候群)に認定されました。
ブログで発信していた患者やその家族が集まって会を創立しました。
現在の会員数は約50名で、寛解により退会する人や新たに発症し入会する人がいるため、増減はあまりないそうです。
千葉大で行っていたレジストリも国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)から研究費をいただき、刷新します。2025年4月から患者さんの登録システムが稼働しました。HPの告知を急いでいるところです。
患者会の活動と課題
患者会の目標
- 治療薬の拡大:POEMS症候群では類縁疾患である骨髄腫の治療で使われているいくつかのお薬が有効であると示唆されています。しかし、患者さんが少ないことから適応外使用を余儀なくされており、全国で受けられる医療に格差が生じております。患者さんの症状に応じて、全国の病院で受けられる治療が増えることを望んでいます。
- 疾患の認知:毎年、神経学会にブースを出しており、昨年は、日本神経治療学会、日本血液学会、日本末梢神経学会にブースを初出展し、今後も様々な学会にブース出展の幅を広げていく予定だそうです。
患者・患者会の困り事
<患者>
- 承認されているお薬がサリドマイドの1剤しかなく、なかなか他の薬をつかってもらえないことです。
<患者会>
- Zoomで交流会を実施しているが、現場感が伝わりにくく、出席者が固定化して盛り上がりに欠けることがある。
- リアルで集まったこともあるが、患者さんが各地に点在しているため、集まっても7〜8名にとどまる。
- どのように患者会を盛り上げたら良いのか、常に模索している。
- Facebookでの活動のあり方や使いやすいホームページの構築、活動資金の確保など課題がある。
Patient and Public Involvement(PPI)の取り組み
PPIとは患者や市民が医療研究や医療政策の意思決定に参画することですが、猪野毛先生が主体となって活動を計画しています。具体的には、レジストリ研究やガイドライン委員を患者会の代表として務めるなどされています。
具体的には、レジストリ研究やガイドライン委員を患者会の代表として務めるなどされています。
今後の展望とまとめ
POEMS症候群サポートグループは、世界中の同じ疾患の方々と協力し、この疾患の治療研究が進み、早期発見、早期治療ができるように日々努力を続けています。
2026年度中に完成予定の診療ガイドラインは、全国の医療機関での適切な診断と治療の標準化に大きく貢献することが期待されています。また、患者レジストリの刷新により、より多くの患者データが集積され、研究の進展や新たな治療法の開発につながる可能性があります。
希少疾患の患者会は、患者数の少なさや地理的な分散、資金面など多くの課題を抱えていますが、オンラインとリアルの両面での活動を工夫しながら、患者同士のつながりを強化し、医療者や研究者との協働を進めています。
このような患者会の存在は、希少難病と診断された患者さんにとって大きな支えとなるだけでなく、疾患の研究や治療法の開発にも不可欠な役割を果たしています。POEMS症候群サポートグループの今後の活動に、さらなる注目と支援が集まることを期待します。